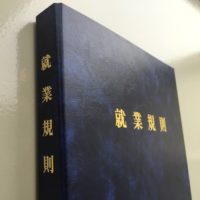8.0 役立情報
企業の年間休日数は平均109.9日に増加
2021年1月10日 8.1人事労務ニュース
就職活動における企業選びの条件として、労働時間や休日を重視する傾向が強まっています。厚生労働省は「令和2年就労条件総合調査」において、年間休日総数や年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得状況の結果を公表しており、自社の状況を一般的な水準と比較することができます。
年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例
2020年12月29日 8.1人事労務ニュース
2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される従業員に対して、付与された年休の日数のうち年5日について、会社が時季を指定するなどして取得させることが義務となりました。ここでは、年5日の年休取得義務の対象者と、年5日の年休取得義務への対応において迷いやすい事例をとり上げます。
多くの従業員を解雇等するときに必要な届出
2020年12月28日 8.1人事労務ニュース
新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇や雇止め等(以下、「解雇等」という)、雇用に対する不安が広まっています。事業主としては雇用の維持に努めることを基本としつつも、状況によっては事業存続のために人員削減を行わざるをえないケースも出てくるでしょう。そこで今回は、一定数以上の従業員の解雇等を行うときに必要な届出についてとり上げます。
情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点
2020年12月28日 8.1人事労務ニュース
労働安全衛生法において、長時間労働やストレスチェックにより一定の基準を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施することが求められています。先月、厚生労働省は情報通信機器を用いて面接指導を行う場合の留意点を改正し、示しました。
新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
2020年12月14日 8.1人事労務ニュース
新型コロナウイルス感染症の拡大により、新規学卒者で内定を出していたにも関わらず、採用内定取消を行わざるを得ない企業が見られるようです。そこで今回は新規学卒者について、内定取消を行う際の注意点をとり上げます。
2021年4月より施行される改正高年齢者雇用安定法
2020年12月14日 8.3 人事労務管理Q&A
坂本工業では、定年を60歳とし、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を導入している。今後、65歳になるベテランの従業員がいることもあり、65歳以降の雇用について社労士に相談することにした。
人事労務管理における「常時使用する労働者」「常用労働者」の定義の違い
2020年12月5日 8.2 旬の特集
人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。
2021年1月より時間単位で取得できるようになる子の看護休暇・介護休暇
2020年12月5日 8.2 旬の特集
育児・介護休業法施行規則が改正され、2021年1月より子の看護休暇と介護休暇について、時間単位で取得できるようになります。
就業規則の届出を本社一括で行う方法
2020年12月5日 8.1人事労務ニュース
就業規則を作成・変更した場合には、事業場を管轄する労働基準監督署に届出を行う必要があります。この届出は原則として事業場ごとに行うことになっています。一方で、複数の事業場がある場合で、すべての事業場で同じ就業規則が適用される場合には、本社で一括して行うことが認められています。
年次有給休暇の平均取得日数は10.1日
2020年12月5日 8.1人事労務ニュース
2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇(以下、「年休」という)が付与される労働者に対して、年5日の取得義務化が開始されましたが、これにより、年休の取得が全体的に進んでいるようです。そこで今回は、先日、厚生労働省から公表された「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」の中から、年休の取得状況や計画的付与制度の導入状況について見ていくことにしましょう。